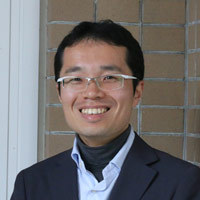------
「地下の生態系は、科学におけるブラックボックスです」と語る、京都大学生態学研究センター准教授の東樹宏和さん。
植物とその根に共生する真菌類の相互作用に着目し、地下生態系の全体像把握に挑んでいる。
東樹さんがその先に見ているものは、森林の再生や農業生態系の設計だ。
今回、多数の生物種で構成されるネットワーク構造を解析し、多種系の生態・進化動態の解明を目指す論文が、Nature Ecology & Evolution の2月号に掲載された。
------

東樹 宏和氏
―― 地下の生態系を中心に研究していらっしゃるのですね。
東樹氏: はい。私は、特に地下に着目して、そこにすむ多様な生物たちがどのような生態系を形成しているのか、その全体像を明らかにしようと研究を進めています。しかし残念ながら、地下の生態系については、その複雑性と重要性の割に研究者が少ないのです。
―― 以前は進化の研究をされていたと伺いましたが。
東樹氏: 大学院では、共進化を研究していました。対象にしたのは、ツバキシギゾウムシという昆虫です。
この虫の雌は、非常に長い管状の口を持っており、その口をドリルのように使ってヤブツバキという植物の実に穴を開け、卵を産みつけます。
しかし皮が分厚い実は、ゾウムシの攻撃に耐え、卵を産みつけられることなく、中の種子が生き残ることができます。
そして世代を重ねていく中で、ゾウムシはますます口を長く進化させ、ヤブツバキの実もますます皮を分厚く進化させてきました。
このゾウムシとヤブツバキの「軍拡共進化(攻撃と防御との間で起こる競争による進化)」という現象を明らかにし、学位を取りました。
真菌類に着目して生態系の研究へ
―― その後、進化学から生態学の研究に移られたのですか?
東樹氏: いえ、移ったというわけではありません。現在は、共進化の研究で培った知見を生かして、生物種間の進化的・生態学的関係性の両方を研究しています。
進化の研究は、研究対象の観察にとてつもなく時間がかかることもあって、通常は、1、2種の限られた数の生物種間の相互作用を研究するのがやっとです。
しかし、現実の自然の中には数多くの生物種が存在しており、それぞれが他の数多くの生物種と相互作用を持っているはずです。
そうした多数の生物種間の相互作用を調べてみたいと思うようになったのですが、多数の生物種を扱う群集生態学と共進化の研究をどうつないだらよいのか、長い間悩んでいました。
現在の研究を立ち上げた頃はちょうど、次世代シーケンシング技術が台頭してきた時期でした。
そこで、特定の遺伝子領域の短い塩基配列を用いて種を特定するDNAバーコーディングによって大量のサンプルの生物を同定し、それをネットワーク理論と組み合わせれば、生物種間の相互作用における「白地図」のようなものが書けるのではないかと考えました。
その白地図のネットワークを基にすれば、調査地における生物種の多様性と潜在的な相互作用網の構造を把握することができます。
そこから、群集や生態系全体に影響を与えそうな種を選び出し、生態学的現象と進化学的現象の両方を詳しく研究していけばよいのではないかと思ったのです。
「全体」を把握した上で、系全体に影響を与え得る「部分」に焦点を絞っていく戦略です。このネットワーク分析の手法を、植物の根に共生する真菌類を主な研究対象として発展させてきました。
―― 真菌類とはカビやキノコのことですね。
東樹氏: そうです。いわゆるキノコと呼ばれるものは、1000分の数mm程度の太さの菌糸が集まって作られた繁殖器官、つまり子実体のことです。
しかし、真菌類の中には子実体を作ってくれないものも多く含まれます。
こうした真菌類が、ほとんどの植物の根に共生しており、その生育に大きな影響を及ぼしているのです。
植物の生長を助けたり植物を病気から守ったりすることもあれば、逆に植物に病気を引き起こしたりすることもある、大事な存在です。
実は学部生のころ、キノコ狩りの学生サークルに入っていました。採集したり、分類したり、料理したりとキノコで楽しんでいましたが、今ではその真菌類の研究をしています。
―― 具体的には、どのように研究を進めていかれたのか、教えてください。
東樹氏: まず、ある場所の植物種と地下真菌類の共生関係の全体像を捉えようと考えました。
山へ行き、植物の根を試料として採取して、そこに含まれるDNAを解析します。
1つの調査地でランダムに何百もサンプリングすれば、その場所に生息する植物と菌の、地下における存在頻度を反映したデータが得られるはずです。
実際に、北海道から屋久島までの3地点で、それぞれ、30種以上の植物と数百種の真菌類との共生ネットワーク構造を捉えることに成功しました。
このような研究で苦労するのは、解析すべきデータ量が多いことです。
そこで、先行研究の共同研究者である田辺晶史さん(神戸大学)が開発されたDNAバーコーディング技術を利用しました。
田辺さんが開発した画期的な理論(QC-auto法)と自動化プログラム(Claident)により、途方にくれるほど膨大な計算時間を短縮する道が開かれました。ちなみに、この理論と実装プログラムを使えば、地球上のあらゆる生物群について、自動同定を行うことが可能です。
ハブ生物種とメタ群集を用いた解析方法を開発
―― それからどのようなことに取り組まれたのですか?
東樹氏: 次に取り組んだのは、その場所に存在するたくさんの生物種の中から、優先的に解析すべき種を選ぶ方法の開発です。
真菌類だけでも数千〜数万種が1つの森や草原の地下に潜んでおり、むやみに実験や観察を行うわけにはいきません。
そこでまず、その生態系で影響力の大きいと思われる生物種を選ぶことが必要になります。
具体的には、どの菌とどの菌がよく一緒に存在しているかという関係性を調べ、ネットワーク内における菌間の関係性を仲立ちする位置にいる種を「ハブ生物種」と定義することにしました。
さらに、複数の異なる場所でのハブ生物種を比較する方法を提案しました。
すなわち、ある場所と別の場所の生態系(ネットワーク構造)を比較する際、それらを合わせたメタ群集を想定し(図1、2)、メタ群集レベルのネットワークの中で重要そうなハブ生物種を見つけ出す方法を提案したのです(図3)。これらをまとめて、今回の論文に発表しました。

図1:3つの局所群集(植物と共生真菌類で構成される)における地下のネットワーク構造
丸の大きさはその生物種の存在頻度に比例する。

図2
3つの局所群集に共通して出現する種を対象にして、3つの群集を連結したメタ群集を考える。

図3:メタ群集レベルでのハブ生物種の位置付け
複数の群集にまたがって分布する種、群集1のみに出現する種、群集2のみに出現する種、群集3のみに出現する種。
真菌類のような微生物は特に、広範囲に分布して、その共生相手(植物)に影響を及ぼすものがいます。地理的な移動性(分布域)と種間ネットワーク内での重要性の両方を考慮した指標を提案できれば、生態系再生や外来種問題、農業における微生物利用といった場面で利用価値が高いのではないかと考えたのです。
―― 生態学と進化学はこれまで融合されていなかったのですか?
東樹氏: 両分野が協力し合うことの重要性は認識されているのですが、それぞれの研究者はどちらかの分野に軸足を置いており、研究上の興味や価値観もだいぶ異なっているように感じられます。
しかし、微生物は生態系の中で短い期間でも進化を遂げますので、数の変化を扱う群集生態学と種の質の変化を扱う進化学の研究方法を融合する必要性を、私は痛感していました。
今回の論文の共著者は、生態学と進化学をつなごうという意思の強い方たちでしたので、大変心強かったです。
両分野の研究者に今回の論文がどのように受け取られるかわかりませんが、両者が協力可能な研究のプラットホームを作ることができたと思っています。
―― それで、Nature Ecology & Evolution に投稿されて......。
東樹氏: 2016年の春頃、Nature Ecology & Evolution の創刊を広告か何かで知り、いよいよNature 関連誌にこの分野のジャーナルが登場するのだと喜びました。
Nature 本誌はもちろんのこと、関連誌にはこの他にも、Nature Microbiology、Nature Plants、Nature Communications などの投稿先候補があり、自分で納得できる成果が得られたら今後も投稿していきたいと思います。投稿先を迷っているときでも、これらのジャーナルの間では論文のフォーマットを変更する必要がないのでありがたいです。
広い視野に立ち、農業に役立つ研究を目指す
―― 今後は、既成概念にとらわれない研究方法の提案を目指していきたいということですね。
東樹氏: はい。リスクを承知で、インパクトのある研究をしたいと思っています。
ゾウムシの研究では、共進化という現象について自分なりに納得のいくまで深く考察できた感がありました。しかし、よい研究対象にたまたま恵まれただけだったのではないかという不安にも駆られ、フロンティアを求めていました。
2010年、京都大学が公募する次世代研究者育成センター(白眉センター)に採用されましたが、その同僚には将来ノーベル賞を取るのではないかという若手研究者もいて、大変刺激的でした。
その刺激をバネに申請した大型予算が採択され、プレッシャーを感じつつも、狭い専門分野にだけ閉じこもることなく、他の分野の人たちの話も聞いて視野を広げることが大事だと気づかされました。
今回の一連の研究で、当初は「そんなことやって何になるの」と、よく言われたりもしたのですが、研究解析方法の提案にまでこぎつけました。
また、真菌類の中で、これまでほとんど研究されていなかった「内生菌」が生態系で重要なハブ生物種であることもわかってきて、研究材料としても今後期待できると思います。
―― 内生菌とは?
東樹氏: 従来は、植物の根に共生する真菌類のうち、菌根菌と呼ばれるグループがよく研究されてきました。
菌根菌とは、植物の根の組織内外に菌根と呼ばれる共生組織を形成する真菌類で、例えば、マツタケもこの仲間です。
実は植物体内には、菌根菌以外にも、内生菌と呼ばれる真菌類がすんでいます。宿主である植物には害を与えないが、機能はよくわかっていないという多様な真菌類です。
内生菌は、これまではほとんどの研究者の興味対象ではありませんでした。ですから、内生菌のDNAデータを、試料中の不要データとして、菌類の研究者から分けてもらえることもあるくらいです。
また、内生菌が植物の性質(野菜の味、酸性土壌での成育)を左右するという報告が増えつつあることも、学会や文献で知りました。
菌根菌と異なり、内生菌は簡単な培地で培養が可能なものが多く、内生菌によって植物の性質や健康状態を操作できるのではないか、そして農業などにも活かせるのではないかと考えています。
―― 今後、研究をどのように展開されるお考えですか。
東樹氏: すでに、内生菌の解析を進めており、内生菌の「仲良しグループ」が存在することがわかっています。
さらに、その仲良しグループの中に、ネットワークのハブとなる種がいることもわかってきており、植物体内で共生微生物叢全体を制御しているのではないかと推測しています。そうしたハブ種が先に植物体内に入り、後から入ってくる種を選んでいたら面白いですね。
今後、ハブ種の菌を割り出し、その菌を植物に接種する実験を計画しています。そのハブによって、農地にいる微生物の中から人間にとって都合のよいものを優先的に植物体内に取り込めるようになるかもしれません。
最終的には、どのような菌類を持った、どのような植物を組み合わせて植えれば、農地として望ましい生態系が築かれ、環境の変化にも強くなるのか、解明していきたいと思います。生態系の設計という挑戦的なテーマで、基礎研究として興奮しますし、応用研究として新たな軸を形成していけるかもしれません。
「農学中手(なかて)の会」というのがあります。農学のさまざまな研究者たちが分野横断的に集まって話合おうという会で、年齢的に「若手」ともいえないからと、「中手」と称しています。
私ももともと農業に興味があったのですが、会に参加して話し合う中で、農業や地球環境に対する問題意識や発想がより具体化してきたと感じています。意気投合した異分野の研究者と連携しながら、人類が抱える環境・食糧問題に取り組んでいきたいと思います。
―― ありがとうございました。
インタビューを終えて
生物の野外観察・採集は大好きな東樹准教授。昆虫から植物、真菌と、いろんな生物を求めてさまざまな生態系を調査してきたそうです。学生時代からのキノコ狩り仲間や飲み友達が、現在の共同研究者に多数含まれているそうです。

Nature Ecology & Evolution 掲載論文
Perspective: 種多様なネットワークとメタ群集レベルにおける生態学−進化学の統合
Species-rich networks and eco-evolutionary synthesis at the metacommunity level
Nature Ecology & Evolution1 : 0024 doi:10.1038/s41559-016-0024 | Published online 24 January 2017
Author Profile
東樹 宏和(とうじゅ ひろかず)
京都大学生態学研究センター 准教授
2003年京都大学理学部卒業
2005年京都大学大学院理学研究科修士課程修了
2007年九州大学大学院理学研究府博士課程修了(博士(理学))
2008年日本学術振興会特別研究員 / 独立行政法人産業技術総合研究所 生物機能工学研究部門
2010年京都大学次世代研究者育成センター(白眉センター)特定助教
2012年京都大学大学院人間・環境学研究科 助教
2015年スタンフォード大学生物学部(米国) Visiting Scholar
2016年科学技術振興機構(JST)さきがけ研究員
2017年京都大学生態学研究センター 准教授(現職)
2010年日本生態学会宮地賞
2010年京都大学「白眉研究者」